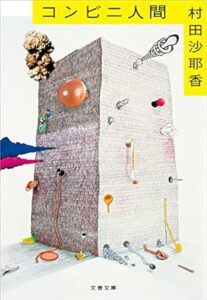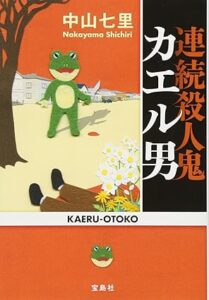- タイトル:正欲
- 著者名:朝井リョウ
- 出版社:新潮社
あらすじ:
自分が想像できる”多様性”だけ礼賛して、秩序整えた気になって、
そりゃ気持ちいいよな。
息子が不登校になった検事・啓喜。
初めての恋に気づく女子大生・八重子。
ひとつの秘密を抱える契約社員・夏月。
ある人の事故死をきっかけに、それぞれの人生が重なり合う。
だがその繋がりは、”多様性を尊重する時代"にとって、ひどく不都合なものだった。
多様性は「だいたい分かっているもの」だと思っていた
多様性という言葉は、もう説明不要なほど使われている。
国籍や性別、LGBTQ+など、違いを認め合うこと。
誰を好きになってもいいし、どんな生き方をしてもいい。
正直、そのあたりはもう理解したつもりでいた。
少なくとも、自分は「分かっている側」だと思っていた。
遅れているとも、偏っているとも、あまり感じていなかった。
それでも、この本はきつかった
[正欲]を読んで、強く残った感覚は反省だった。
ストーリーがどうこう、というよりも、
自分の視野がいかに狭く、理想論の中にいたかを突きつけられた。
多様性について語る資格が、本当に自分にあったのか。
そんな問いが、読後ずっと残っている。
「正しい性欲」という思い込み
この作品では、人が何に興奮するのか、というテーマが深く扱われている。
それは、教科書的な「性」からはかなり外れたものも含まれる。
読んでいる最中、正直こう思った。
「変わった人だな」「理解しづらいな」と。
ただ、その瞬間に気づいてしまった。
では、自分の興奮は“正しい”のか。
多数派にいるから、健全だと言えるのか。
いやいや、それでも犯罪はダメでしょう
もちろん、どんな欲望でも許されるわけではない。
他者を傷つける行為や、犯罪は論外である。
だからこそ、
「そこは一線を引くのが常識では?」という反論は自然だと思う。
それでも残る、居心地の悪さ
ただ、この本が突きつけてくるのは、
その線引き以前の話だったように感じた。
自分は無意識のうちに、
「これは理解できる多様性」
「これは見たくない多様性」
そんな仕分けをしていなかったか。
受け入れると言いながら、
実は排除したあとに「多様性」と呼んでいただけではないか。
その問いが、じわじわ効いてくる。
多様性を語る前に、立ち止まる
多様性とは何か。
改めて考えると、答えは出ない。
ただ、自分が「正しい側」に立っているという感覚は、
かなり危ういものだった気がする。
理解できないものを前にしたとき、
自分はどんな顔をしているのか。
その違和感を、しばらく抱えたままでいたいと思う。