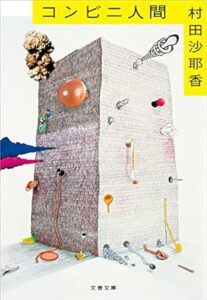- タイトル:世界99 上
- 著者名:村田沙耶香
- 出版社:集英社
あらすじ:
この世はすべて、世界に媚びるための祭り。
性格のない人間・如月空子。
彼女の特技は、〈呼応〉と〈トレース〉を駆使し、コミュニティごとにふさわしい人格を作りあげること。「安全」と「楽ちん」だけを指標にキャラクターを使い分け、日々を生き延びてきた。
空子の生きる世界には、ピョコルンがいる。
ふわふわの白い毛、つぶらな黒い目、甘い鳴き声、どこをとってもかわいい生き物。
当初はペットに過ぎない存在だったが、やがて技術が進み、ピョコルンがとある能力を備えたことで、世の中は様相を変え始める。