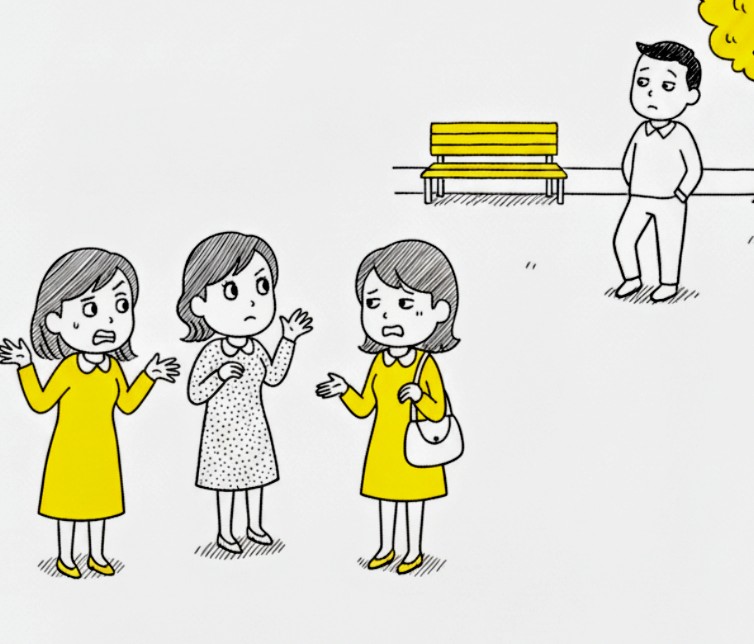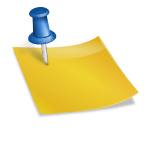目次
【お悩み相談内容】悪口は“共感と発散”なのか?
最近、子育てや夫婦関係について学びたいと思い、女性が多く参加している子育て系のオープンチャットを見ています。その中で感じた違和感について、率直に聞いてみたいと思いました。
チャット内では、子育ての工夫や情報交換もありますが、それ以上に、配偶者に対する不満や愚痴が多く投稿されています。家事や育児への不満、仕事への理解不足といった話題だけでなく、「一緒にいるのがつらい」「生理的に受け付けない」といった強い言葉も目にすることがあり、正直かなりのカルチャーショックを受けました。
義理の家族や実親に対する不満については、どうにもならない状況での気持ちの吐き出しとして理解できる部分もあります。ただ、配偶者に対する言葉がここまで強くなると、「関係を続けること自体が相当しんどいのではないか」と感じてしまう内容も少なくありません。
もちろん、経済的な理由や家庭の事情などから、簡単に別れるという選択ができない人もいるのだと思います。それでも、最終的な行動として「悪口を言う」という形に落ち着いているように見える点に、戸惑いがあります。これは、男女の思考やコミュニケーション文化の違いなのかもしれない、と考えるようになりました。
実際、子育て情報をもっと共有できたらと思い、「不満だけでなく、役に立つ情報交換もできないか」といった趣旨の呼びかけをしたところ、強い反発を受けました。管理する立場の人からも、「愚痴と悪口の境界は曖昧で、それを制限されると嫌な気持ちになる人もいる」と説明されました。
ただ、投稿の中には、「配偶者の行動が気持ち悪いと感じる」「見ていて受け付けない」といった表現もあり、私にはそれが単なる愚痴ではなく、明確な悪口のように見えてしまいます。そして、その言葉を向けられている側の気持ちについては、あまり触れられていないように感じます。
女性同士の場では、「共感」や「発散」が重視されていて、それがこのような形で表れているのかもしれません。ただ、これまで主に男性中心の環境で育ってきた自分にとっては、その文化の違いに驚き、どう受け止めればいいのか分からなくなっています。
こうした違和感は、私が過敏に反応しているだけなのでしょうか。それとも、立場や文化の違いから生じる自然な感覚なのでしょうか。率直な意見を聞いてみたいです。
にったんの回答(個人的見解)
どれだけ生活が進化しても、本能は残るのかもしれません。
ここで言う本能は「女性」一般ではなく「出産を経験したママ」に近いかもしれません。
妊娠出産期に分泌されるオキシトシンは、身近な存在を強く「仲間」と感じさせる可能性があります。
赤ちゃんを守るための自然な働きとして理解できるかもしれません。
裏面として、仲間以外を「敵」と感じやすくなる局面もあるのかもしれません。
もし産前産後にパパが「敵」側に判定されると、愚痴や悪口の対象になりやすい可能性があります。
多くのママは無自覚で、頑張るパパが何をしても不足に見える時期があるのかもしれません。
授乳が終わっても、その時期の心的プログラムが残ることも考えられます。
だからこそ、パパが一時的に「女友達役」を演じる発想も有効かもしれません。
評価や正論より、共感と観察を優先します。
「大変だったね」を先に置き、提案は短く具体的に。
その積み重ねが、次のパートナーシップへ橋をかける可能性があります。
NLP的補足:反復で“心のパターン”は変えられる
NLPでは、人は反復でプログラム化されると捉えます。
産前産後に「同じ接し方」が続くほど、不一致は強化されがちです。
「旦那=嫌な人」という連想も、日々の積み重ねで固まるのかもしれません。
逆に言えば、望む関わりの反復で、再学習は起こりうるはずです。
完璧は不要です。
小さな成功体験を反復し、連想を書き換えます。
二人で合図と手順に合意できれば、行動は続きやすくなります。
「続けられる仕組み」を先に作ることが鍵かもしれません。
まとめと問いかけ
悪口は、共感と発散の“出口”に見える時があります。
ただ、出口が習慣化すると、関係の再建は遠のくかもしれません。
共感を絶たず、悪口の代替行動を設計すること。
今日からできる一手を、まずは一緒に試してみませんか。
問い:
① 明日からの“共感タイム”は何分なら続けられますか?
② 感謝の具体例を、今夜3つ書けますか?
③ 衝突時の合図は、どんな言葉が安全でしょう?