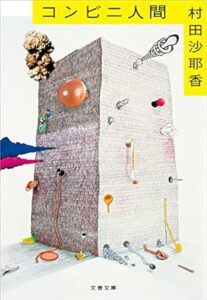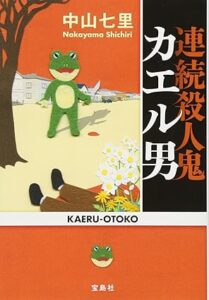- タイトル:授乳
- 著者名:村田沙耶香
- 出版社: 講談社文庫
あらすじ:
受験を控えた私の元にやってきた家庭教師の「先生」。授業は週に2回。火曜に数学、金曜に英語。私を苛立たせる母と思春期の女の子を逆上させる要素を少しだけ持つ父。その家の中で私と先生は何かを共有し、この部屋だけの特別な空気を閉じ込めたはずだった。「――ねえ、ゲームしようよ」。表題作他2編。
家族の食卓は、安心できる場所だという前提
家族で食事をしている時間は、どこか穏やかで、感情が行き交う場所だと思われがちだ。
笑えば笑い返され、話しかければ何かしらの反応が返ってくる。
少なくとも、無言のまま感情が凍りつくような場面は、例外だとされている。
夫婦で向かい合い、子どもたちがその周囲にいる。
そういう配置自体が「うまくいっている家族」の象徴のように語られることも多い。
だからこそ、その場で感じる違和感には、名前がつきにくい。
「感情がないように見える顔」が、気になってしまった
食事中、何か面白いことを言おうとしたとき。
ふと向けられる、何も乗っていないような表情がある。
怒っているわけでも、笑っているわけでもない。
うんともすんとも言わない。
能面に近い、感情の起伏が読み取れない顔。
その表情を、妻以外の人に向けられた記憶はほとんどない。
[授乳]を読んで、線がつながった気がした
村田沙耶香さんの『授乳』を読んだとき、その顔が思い出された。
作中には、少し不思議で、どこか現実から浮いているような人物が多く出てくる。
その中に、強く印象に残る母親の表情が描かれていた。
父親の一挙手一投足をじっと観察し、
その逆を行くためだけに相手を見つめる顔。
それは、愛情でも嫌悪でもなく、もっと乾いた何かだった。
その描写を読んだ瞬間、ぞっとした。
「あのとき見ていたのは、この顔だったのかもしれない」と感じてしまった。
いや、考えすぎでは?という現実的な声
もちろん、考えすぎだと言われれば、それまでだと思う。
本人に聞いても「別に」と返ってくる。
疲れているだけ、ぼーっとしていただけ、そういう可能性もある。
日常の中で、すべての表情に意味を見出そうとするのは、少し重たい。
本に引っ張られすぎているだけかもしれない。
そうやって片付けることも、できなくはない。
それでも、見なかったことにできない違和感
ただ、その顔を向けられた瞬間の空気は、確かに違っていた。
不満という言葉では足りない。
評価や判定に近い何かが、そこにあったような気がする。
しかも厄介なのは、本人ですら無自覚かもしれない点だ。
意識的な怒りではない。
もっと深いところで、相手を観察している視線。
男性は、相手の内側を読むのが致命的に下手なのかもしれない
この作品を読んで強く残ったのは、その感覚だった。
男性は、相手の内的な動きを読み取ることが、驚くほど苦手なのかもしれない。
表に出た言葉や態度だけで、理解したつもりになっている。
『授乳』の主題とは、たぶん少しずれている。
それでも、自分の中では、そこに強く線が引かれた。
ページにアンダーラインを引くように、感覚が刻まれた。
答えは出ていない。
ただ、あの顔を「なかったこと」にするのは、もう難しい気がしている。